ここ数年、日本では「物価が上がっているのに給料が上がらない」という声が各地から聞こえてきます。
スーパーに行けば食品が、ガソリンスタンドに行けば燃料が値上がりし、家計への圧迫感は強まる一方。
一方で、賃金の伸びは思うように感じられず、「インフレなのに豊かにならない」現象が起きています。
今回は、物価を示す「コアCPI」や「コアコアCPI」、そして「実質賃金」のデータをもとに、その背景を解説します。
■ コアCPIとは?物価の「基調」を測る指標
CPI(消費者物価指数)は、一般家庭が購入するモノやサービスの価格の変動をまとめた指標で、「物価の上昇率=インフレ率」を測るものです。
しかし、CPIには野菜や果物など季節によって値動きの激しい生鮮食品も含まれているため、短期的なブレが大きいという欠点があります。
そのため、日本では「生鮮食品を除いたCPI」=コアCPIを用いて、物価の基調的な動きを分析します。
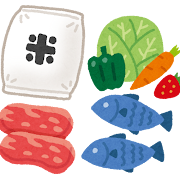
さらに、「生鮮食品とエネルギー(電気・ガス・燃料など)」も除いたものをコアコアCPIと呼び、より安定的な物価動向を測るために使われます。

■ 日本のインフレ率の現状(2025年時点)
総務省の統計や民間調査によると、2025年半ばの日本の物価動向は次のようになっています。
- コアCPI(生鮮食品除く):前年同月比+3.1%(2025年7月)
- コアコアCPI(生鮮食品+エネルギー除く):前年同月比+3.4%(同月)
この数値は、日本銀行が目標とする「物価上昇率2%」を明確に上回る水準です。
つまり、エネルギー価格や生鮮食品を除いても、広範な分野で物価上昇が続いているということです。
ところが、これと同時に発表されている「実質賃金」のデータを見ると、まったく違う姿が浮かび上がります。
■ 賃金は本当に上がっているのか?
厚生労働省「毎月勤労統計調査」によると、2025年の名目賃金(現金給与総額)は前年同月比+2〜3%の伸びとなっています。
表面的には「賃上げが進んでいる」ように見えますが、ここに物価上昇率を加味すると様相が一変します。
同年の物価上昇率(コアCPI)が+3%台で推移しているため、**実質賃金(=名目賃金−物価上昇分)**はマイナス。
例えば、名目+2.5%・物価+3.3%なら、実質賃金は▲0.8%です。
厚労省の統計でも、実質賃金は2025年春時点で前年同月比▲2.8%と減少しており、購買力はむしろ低下しているのです。
■ なぜ賃金が物価に追いつかないのか?
① コストプッシュ型インフレだから
今回のインフレは、需要が強まって企業が儲かっているからではありません。
原材料価格やエネルギーコスト、円安による輸入価格の上昇など、コスト要因が主因です。
企業は仕入れコストが上がった分を販売価格に転嫁していますが、利益を増やす余裕はほとんどなく、賃上げに回せる資金が限られています。
② 労働市場の硬直性
日本では労働市場の流動性が低く、転職や交渉を通じて賃金を上げる仕組みが機能しにくいのが実情です。
欧米では、労働者がより条件の良い職場に移ることで、企業側が引き留めや採用競争のために賃金を上げざるを得ません。
しかし日本は、終身雇用や年功序列が根強く、転職率も低いため、「賃上げ圧力」が弱いのです。
③ 中小企業の価格転嫁力が弱い
日本企業の約99%は中小企業。
多くが大企業の下請け構造にあり、原材料や人件費が上がっても、納入価格を引き上げにくい立場です。
結果として利益率が低下し、従業員の給与に還元できないという悪循環に陥っています。
④ デフレマインドの根強さ
長年のデフレ経験により、日本企業も消費者も「値上げ=悪」「節約=正義」という意識を強く持っています。
企業は値上げをためらい、消費者は支出を抑えるため、需要が伸びにくく、企業が賃上げできる経済環境が育ちにくいのです。
⑤ 実質賃金のマイナスが続く構造
名目賃金がわずかに上がっても、物価上昇率がそれを上回れば実質賃金は減ります。
これが続くと、家計は節約志向を強め、消費が減退し、企業の売上も伸びにくくなる――
という負のスパイラルが生まれます。
日本はこの悪循環から完全に抜け出せていないのが現状です。
■ 賃金と物価の乖離をデータで見る
実際の統計では、物価上昇(CPI)は2025年半ばで約+3%台、
名目賃金の伸びは+2〜3%程度にとどまっています。
この「わずか1%前後の差」が積み重なることで、
実質賃金は1年以上連続で前年割れ。
これは家計の実感と一致しており、
「給料は上がっても生活が苦しい」という声が多い理由でもあります。
■ それでも賃金を上げるために必要なこと
では、どうすれば賃金が物価上昇に追いつくのか。
単純に企業に「賃金を上げろ」と言うだけでは解決しません。
経済全体の構造改革が必要です。
- 生産性の向上:
デジタル化・自動化・人材投資を通じて労働生産性を高め、利益の源泉を増やす。 - 価格転嫁の正常化:
下請け企業も正当なコストを反映できるよう、取引慣行を是正する。 - 労働市場の流動化:
転職や副業を通じて労働者がより良い条件を選べるようにする。 - デフレマインドの転換:
「値上げ=悪」という意識を改め、付加価値の高い製品・サービスには正当な価格を支払う文化を広げる。 - 政府の支援政策:
中小企業向けの賃上げ促進税制や、補助金によるコスト負担軽減も不可欠です。
■ まとめ:物価より賃金が上がる経済へ
2025年の日本は、表面上はインフレが進みつつも、
その中身は**「コスト上昇による苦しいインフレ」**であり、
賃金の上昇がそれに追いつかない「生活防衛型インフレ」とも言えます。
本来、理想的なインフレとは「企業の収益拡大→賃金上昇→消費拡大→経済成長」という好循環です。
しかし今の日本は、「原材料高・円安→コスト転嫁→家計圧迫→消費減退→賃上げ鈍化」という悪循環に陥っています。
この構造を断ち切るには、単なる賃上げ要請ではなく、
生産性の向上・価格転嫁の正常化・意識改革という複合的なアプローチが必要です。
物価上昇が「苦しみ」ではなく「豊かさ」に結びつく社会へ。
日本経済は今、その分岐点に立っています。

コメント